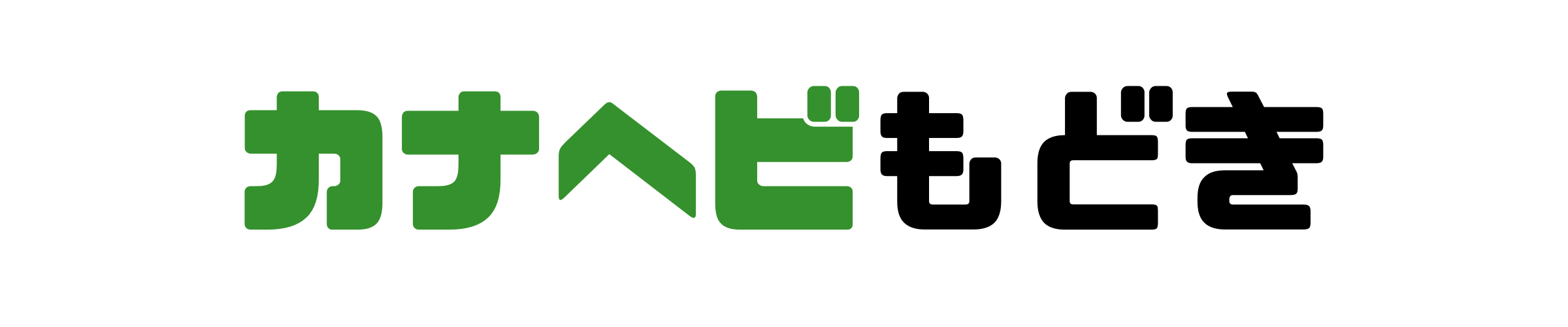琵琶湖ワカサギ食べてみた 余呉湖じゃなく川でも捕れます

2月に琵琶湖の流入河川でワカサギを捕りました。
ワカサギ釣りと言えば、氷の張った湖に糸垂らして釣るイメージですが、川でも取れます。
実際に筆者の住む滋賀県では、余呉湖(凍らない)でワカサギ釣りを楽しめますが、漁業権の無い川で捕ればお金がかかりません。
今回はそんなワカサギの生態や捕り方などをまとめてみました。
ワカサギとは?

成魚で6~11㎝に達します。シシャモに近い仲間です。
食性は肉食で、動物プランクトン、稚魚、魚卵などを食べています。
ワカサギの生息環境と分布
天然分布は太平洋側で茨城以北、日本海側で島根以北ですが、食用魚として人気なため、全国の湖沼へ放流されました。
そのため現在では、南西諸島、伊豆・小笠原諸島を除く全国で見られます。
ワカサギの一生
ワカサギは本来、河川と海を回遊して過ごしますが、湖沼に閉じ込められて一生を淡水で過ごすものもいます。
3月頃、川や湖岸に産み付けられた卵から孵化します。大きさは5㎜程度です。
孵化したワカサギは主に夜に、海または湖に下ります。
餌としては、ワムシなどの動物プランクトンを食べます。
↓
春頃に体長3㎝程度の稚魚になります。
この時期には、ミジンコ等の大型の動物プランクトンやユスリカなどを食べます。
↓
夏~秋にかけて、体長6㎝程度の成魚になります。
成魚になると、エビの幼生やハゼ類の稚魚も食べるようになります。
↓
秋~冬の間には体長が10㎝を越えるものも出てきます。
この時期に精巣と卵巣が発達し始めます。
↓
1月~ワカサギの卵を産む時期が始まります。
この時期にワカサギは、卵を産むために川を遡上してきます。
卵を産む主な所は、河川や湖岸の浅瀬の砂礫地です。
↓
卵を産んだ後には、多くの個体が天寿を全うします。
しかし一部の個体は、2~3年生存して、再び卵を産みにやって来ます。
琵琶湖のワカサギ捕り方
私が捕ったのは、琵琶湖の北の方の某流入河川です。
そこまで河口というほどの場所ではありませんでしたが、卵を産む条件の砂礫地でした。
ワカサギは夜に遡上してくるため、取りに行ったのは夜の7時から10時くらいです。
ライトの明かりに反応して逃げるので、あまり水面には光を当てないようにしましょう。
方法は投網で捕りましたが、何回か投げて1~5匹ずつくらい入りました。
ワカサギは群れで動いているので、同じ川で捕っていても、全く捕れていない人もいました。
また琵琶湖産のワカサギは、余呉湖産の約2倍の体長を持つことが知られています。
これは餌環境などの発育環境が、琵琶湖の方がより良いためであると考えられています。
ワカサギ食べ方
この日は40匹程度捕れたので、いくつかの料理を作りました。
1.生

しっかりした味はあるけれど、やはり淡白なので他の料理にした方が良いかも。
2.南蛮漬け

普通に美味しかったけれど、ワカサギでやる必要は無いなという印象です。
3.佃煮

身が柔らかいので少しやりにくいです。こちらも普通に美味しかったけれど、ワカサギには向いてません。
4.塩焼き

シンプル且つ最強です。
ワカサギの味がよく分かりますし、卵の入っているやつはししゃもみたいな感じでした。

5.天ぷら
こちらも塩焼きと並んで最強です。
ただワカサギ本来の味を味わいたい場合は、塩焼きの方が良いかもしれません。
琵琶湖のワカサギ事情
滋賀県にワカサギは本来生息していませんでした。
現在びわ湖で見られる物は、霞ヶ浦などから移植されたものです。
すでに琵琶湖で定着しているワカサギですが、アユとの餌資源の競合や、アユ稚魚への補食の影響が懸念されています。
一方ではすでに地域の重要な水産資源となってしまった背景もあり、外来種であるワカサギとの付き合い方が問われています。
琵琶湖ワカサギまとめ
以上がワカサギの生態と琵琶湖のワカサギについてでした。
今では全国の湖沼に広がっているワカサギですが、もともとは海と川を回遊する魚なんですね。
氷の上で釣るワカサギのイメージが強いですが、そちらの方がイレギュラーな存在なわけです。
琵琶湖ではアユとの競合が懸念されていますが、詳しい影響についてはまだ分かっていません。
ただアユへの悪影響が認められたところで、更なる放流を禁止するくらいしかできることは無さそうですけどね。
やはり安易な外来種の移入は慎むべきです。